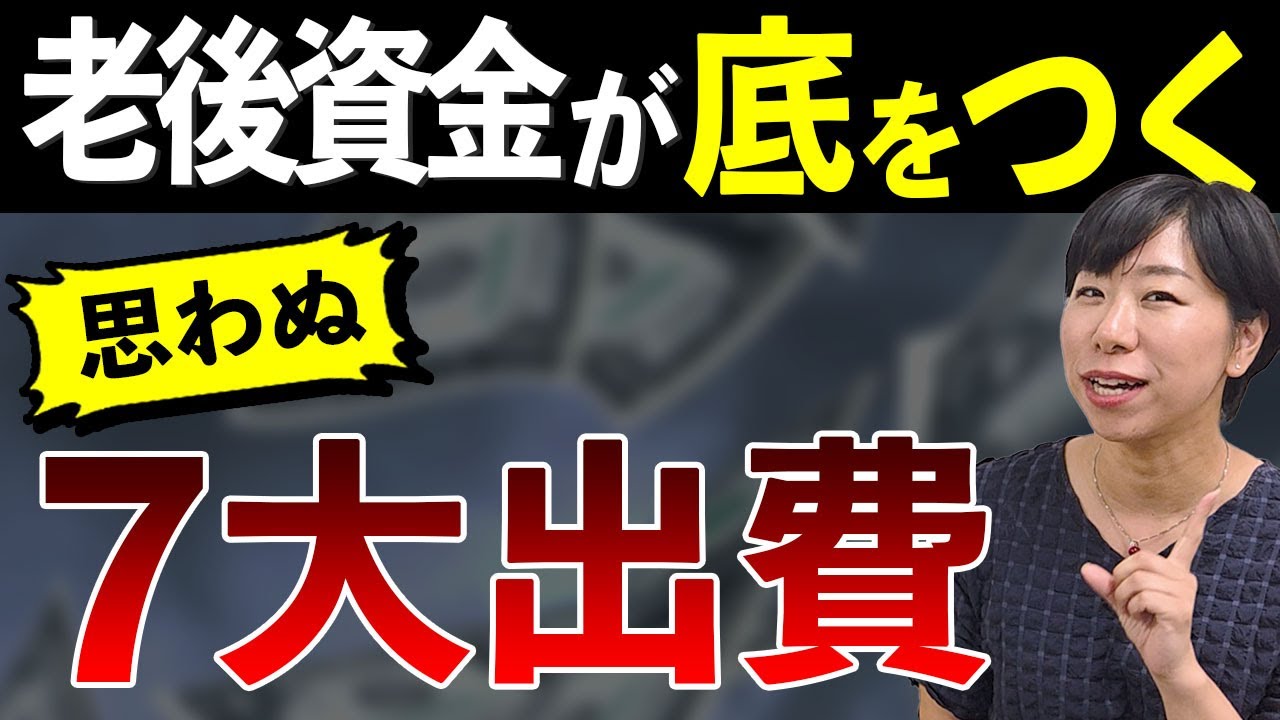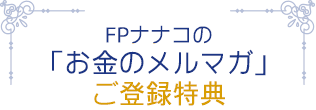今日のテーマは、老後資金が底をついてしまう――つまり、老後に予想外の支出で貯蓄が一気に減ってしまうような出費についてです。
人生の三大資金と言われ、早めに準備しておきたいまとまった資金は「住宅資金」「教育資金」「老後資金」です。
住宅や教育は借入れをして後から返すという選択肢もありますが、老後資金を借り入れるのは難しいのが実情です。
だからこそ、今の自分が老後の自分を支えるために計画を立てておく必要があります。
老後の支出としてどのようなものを見込めばいいか、確認しておきましょう。
この内容を動画で見る方は▼こちらから。文字で読みたい方はこのままお進みください。
老後不安を減らす第一歩
老後はまだ先のことに感じられる方も多く、しかも老後の期間は20年、30年と長くなることがあるため、どのくらい準備すればよいか分からず漠然と不安を抱えている方が多いです。
ただ、老後の生活は基本的に今の生活の延長線上にあることが多いので、まずは「収入と支出のバランス」を確認することが最初にやるべきことです。
支出は現役時代より減ることが多いですが、必要額やいくらあれば安心かは家庭ごとに全く異なります。
平均値に頼らず、まずは我が家の現在の支出を把握しましょう。
今の生活で何にどのくらい使っているかが分かっていれば、老後にその支出が減るのか増えるのかはおおむね推測できます。
そしてその生活を支える収入の柱は年金です。
「ねんきん定期便」や「公的年金シミュレーター」を活用して見込み額を計算してみましょう。
支出と年金見込みの二つをざっくりでも把握しておけば、不足する分がどの程度かが分かり、目標が定まりやすくなります。
目標が定まれば「今何をすべきか」「その時に何ができるか」を考えやすくなり、不安を小さくできます。
まずはここまでやってみてください。
とはいえ、ここで計算した金額はあくまで「年金で不足する生活費」の部分にすぎません。
そこに向けて蓄えを作っていても、生活費以外の想定していなかった出費で一気に貯蓄が減ってしまうことがあります。

1)医療・介護にかかる費用
現役のときは病院に行く機会が少ない方でも、年を重ねれば病気になる可能性は高まります。
日本は公的医療保険がしっかりしているので、保険適用の医療で破綻することは考えにくいですが、長期入院や大きな手術、あるいは保険適用外の治療(例:一部の先進医療や自由診療など)になると負担が大きくなります。
また、民間の医療保険に加入していない、あるいは65歳になると保障が大幅に減るような契約をしている場合は、医療に使えるお金を別途蓄えておく計画が必要です。
介護についても公的介護保険はありますが、介護をすべて公的保険だけでまかなうのは難しいことが多く、家族での負担が長引くケースもあります。
目安としては、介護に備えて1人あたり500万円〜600万円程度を備えておくと安心、という考え方もあります(もちろん必要額は状況により大きく変わります)。
2)住まいに関する支出
住宅ローンを完済してしまえば住居費はぐっと下がりますが、最近は70歳や75歳まで続くローンを組んでいる人もいます。
退職金などで慌てて残債を返そうとしてしまうと、老後資金が急に減る可能性があります。
理想的には65歳までにローンを返済できる金額を老後資金とは別に準備しておきたいところです。
またローンがなくなっても、住み続ける限りは維持費(屋根・外壁のメンテナンス、水回りのリフォームなど)が必要になります。
これらはまとまった金額になることが多いです。
分譲マンションなら築年数に応じて修繕積立金が上がったり、途中で大規模修繕が必要になって追加負担が発生することもあります。
今のうちから修繕計画や積立金の予定を確認し、自分が老後を迎えた頃にどうなっているかを見ておきましょう。
さらに、定年のタイミングで地元に戻る・住み替えを検討している場合は、現住居が高く売れなければ新たな費用がかかる可能性があります。
こうした計画も早めに考えておくと安心です。

3)家族・親族への支援費用
自分たちの介護だけでなく、親の介護にお金がかかるケースや、独居の親族(叔父・叔母など)への支援が必要になる場合もあります。
最近問題になっている「8050問題」に代表されるように、働けない子どもへの支援が長期化し、金銭的負担が重くのしかかることも考えられます。
早い段階で、利用できる支援制度や窓口の情報を集めておくことも勧めます。
また、離婚して戻ってきた子どもの生活を支援したり、孫の教育費を出す必要が出てくることもあります。
資産を若い世代に移転するのは有効な手段ですが、一度渡すと後から取り戻すのは難しいため、金銭支援をする場合は計画的に行いましょう。
4)災害による出費
地震や水害などの自然災害はいつ起こるか分かりません。
火災保険には加入している住宅が多いと思いますが、地震保険の加入率はまだ低い傾向にあります。
住んでいる場所や住宅の構造によって必要性は変わりますが、老後にまとまった出費が発生すると立て直しが難しくなるため、災害リスクに備えた保険や現金の備えを検討しておくことが重要です。
自動車が必須の地域では、洪水や水害で車が被害を受けるリスクも深刻です。
現金で備えておくのは自由度が高く確実ですが、老後にまとまった現金を出すのは心細いため、車両保険などの契約内容も確認しておきましょう。
5)お墓に関する費用
若いうちはあまり考えないかもしれませんが、年齢を重ねると「お墓をどうするか」は大きなテーマになります。
遠方にある実家のお墓の管理が難しかったり、自分はそこに入るつもりがない場合、「墓じまい」や改葬、永代供養などの選択肢が出てきます。
お寺に払う離檀料や墓じまいの費用、遺骨の取り扱いに関わる手続き等、かかる費用の幅は広いです。
また、お寺とのやり取りが難しい場合は墓じまいを代行してくれる業者に依頼することもできますが、その場合も費用が発生します。
高齢になってからだと体力的にも大変ですし、兄弟姉妹など関係者の状況確認も必要になるため、早めに具体的な計画を立てておくことをおすすめします。

6)ペットにかかる費用
人間の医療には公的医療保険がありますが、ペットの医療費は民間の保険に加入していない限り全額自己負担が一般的です。
ペットも年を取れば病気になる可能性が高くなり、治療費やフード、介護用品など、想像以上に費用がかかることがあります。
家族の一員として最後まで大切にするためにも、ペットにかかる費用も見込んでおくと安心です。
7)その他の日常的な支出(通信費・保険料など)
老後のまとまった支出ではないものの、日々の支出がじわじわと生活を圧迫することがあります。
代表的なのが通信費や保険料です。
通信プランは複雑で、よく分からないままオプションに加入してしまい、不要な出費が続いているケースがあります。
定期的な見直しの習慣をつけ、販売する側の人以外にも相談できる窓口を確保しておきましょう。
保険も、年齢が上がってから加入すると保険料が高くなるため、必要性をよく見極めておかないと無駄な保険料を払い続けることになりかねません。
こちらも健康なうちに一度しっかりと見直し、定期的に確認・見直しをするようにしましょう。
老後の不安は「見通し」が解決する
老後資金は遠くに必要な資金であるため、漠然と不安に感じることが多いでしょう。
いますぐに確定できることばかりではないからです。
しかし、不安は「見通し」を持つことでかなり小さくできます。
「まさか」「思っても見なかった」と思うことを減らしていけば、金額の多寡はあれど「大体が想定のうち」となります。
今日ご紹介した7つの項目について、自分はどうか、どれくらい備えがあると安心かをざっくりでも良いので見通しを立ててみてください。
早めに計画して備えることで、安心して老後を迎えられるように準備していきましょう。